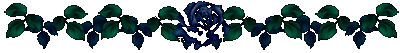
YUME-MABOROSI
およそ一年半にわたる洋行を終えて戻ってきたあのひとはさらに陰影を増し、都下で闊歩する我々の目を惹きつけた。もっとも帰朝したとはいえ家に閉じこもりきりで、日の下(もと)に姿を現すなどはしておらず、だから肌の白さは相当なものになっている。
本当の“静養”をした方がいいのではないかと、我々の間で囁かれて数ヶ月が経つ。だから、安息を妨げるかのように闇夜に紛れて訪れる人影を目にする度、私は胸の辺りを押さえては浅く呼吸を繰り返すのだった。
「…っ、はぁ……」
危険だ、と思う。あのひとの体が。あのひとの心が。
が、自分にはどうすることもできない。ただ命じられるままに沸き立つ太政官を観察し、報告するしか、あのひとの信頼に報えない。
そう思ってうめくと鼻頭に柳の葉が触れ、ふらつきながら夜道を歩く自分に気がついた。
溜め息をついて空を見上げた。星が微かに瞬いて、やがて動乱を迎えようとする世界に、せめてもの慰めを降らせてくる。
畳のうえに投げ出すようにして倒れ込んだ細身を、従道の軍人らしい太い腕が受け止めた。
元々丈夫とは言えない肉体も勿論だが、誰よりも肝が据わっている筈の精神が病んでいる。冷たいはずの肌が従道の腕のなかで、時折病に冒されたときのように熱を生んで従道を驚かせては、自分の大久保に対する想いと…大久保の想いの違い―――深さの違い―――に彼を突き堕とすのだった。
自分は兄にはなれない。
昔から従道をある意味苛んできた鬱蒼がここにおいても尚、従道を縛り付けて離さなかった。こうしてふたりきりで過ごす時のなかにいても。
「……そげんこつ、」
やめなされ、と言って従道は鋭い歯で噛まれている白い指を大久保の口から引き抜いた。蜻蛉のように細いそれに大久保の血が絡んで落ちてゆくのを目にすると、ついさきほど潰えたはずの雄としての欲が、再び己のなかで再び吹き返すのを感じてしまう。
「ゆっくぃ、お休みなされ。夜も更くっ」
望まれたとはいえ、やつれきった大久保の体力では三度目は無理だろう。そう思って従道は己を戒め、大久保を抱き上げて床に向かう。
「……ッ!」
脱力していたはずの大久保が、突然鋭い爪を従道の胸に突き立て、血が滲んだ。腕に抱き上げられている体とは対照的な、従道の厚い筋肉が盛り上がって大久保の爪を受け止める。
「どうしたのですか」
驚いて見下ろすと、いきなり背中に両腕を回してきた。また、爪を立てる。着物の上なのに刺さっている感覚さえ伴うのだ。
傷つけないようにゆっくりと体を横たえ、寝かせつけようとする。が大久保は回した腕を離そうとはしなかった。薄い胸に再び重なった従道の胸が、熱くなる。大久保の肌は冷たいのだが。
柔らかい髪の毛がふわふわと従道の頬や顎を撫でる。そこから何か――――どちらかというと振る舞いの大人しい従道に真実宿っている激情を彷彿させる彼の香りが漂ってきて、従道は息を詰めた。
大久保はまだ腕に力を入れたままである。自然従道が、横たわる大久保の上に覆い被さる格好になった。
「潰れますよ」
従道は、夜は薩摩語を使わない。先ほどは感傷に理性を喰われてしまって、つい薩摩語がでてしまったが。
大久保は瞼を半分開けて従道を―――否―――従道のそっくりな声で思い出したのであろう、兄を求めていた。
兄・隆盛が大久保を訪ねなくなって既に百日以上を数える。その間大久保は廟堂には一度も出ず、一月ほどの休暇を得て出掛けたとはいえ観光とは名ばかりで、心身を消耗してきただけであった。
そして今日、岩倉が大久保邸を訪れた。
兄と対決して欲しいという。
馬鹿なことを、と従道は思った。渡韓を迫る兄と対抗できるのは大久保しかいないことは、公卿の頭でなくとも理解できる。西郷から逃げ回っている木戸では役不足だ。
が、あのボンクラどもには、このひとにとってそれがどういうことか、一片もみえていない。小さく体を震わせて一時の幻想に酔いしれ、…同時に、目の前の現実を見過ごせないこのひとの、本質をわかっていない。
「いけません」
こうして自分を離さない大久保が何を求めているのか、従道にはわかる。他のすべても、わかっている。
だからこそ、従道は断らなければならなかった。
洋行から戻って以来、大久保はやせ衰える一方である。彼が半ばまで建設した国が明らかに様相を変え、彼の最も厭う凶暴な国を目指しているだけでなく、その原因を拵えたのが隆盛であることと、その隆盛を己の手で潰さなければならない未来が待ち受けていること、…そして己が生き残るだろうことに、絶望を感じてやまない。
夫人に訊けば食事は三度きちんと胃に納めているという。とすれば病が悪化したか、吐いているかどちらかだろう。いずれにしろ、こんな貴方を痛めつけるわけにはいかない。
「さぁ、お眠りなさい」
「………」
元々、従道は寝付けない大久保に休息を与えるために彼の望みに応えている。酷く考え込んで深みに嵌る癖をもつ大久保は、いったん思考し出すと自覚のないままに軽く一日は費やした。増して今回には思考に絶望が加わっていた。
こけた頬が異様に白い。たったいま抱いた体はいまにも闇に透けそうに細くて、このままどこかへ連れ去ってしまいたい。京都にいたころの兄になって、このひとを一晩中抱いていられたら自分はどれだけ満たされるだろうか。
「…もう、いちど…だけ……」
灰色の瞳を閉じたまま、唇だけで大久保が求めてきた。
―――――残酷な方だ。あの兄に、たったひとり真実愛されただけのことはある。
従道は東京に入った辺りから、本気で、兄と言う人は性質として過剰に巨大であるが故に、危険とみなしてきた。それは言い方を変えれば、動乱にしか生きられない人間ということである。
動乱を、兄は生き抜いた。互いに二人でいられたからこそ、あの回転は為ったのである。
その二人の間柄が急激に色彩を変えたのは、五月に大久保が帰国してから。
あのときはこんな貴方ではなかった。従道だけでなく、政府にいる同僚等が囁きだしてから一層、大久保は疲労しきった。そのうち横になっても眠れぬ日が続き。
多くの薩人のように号泣できればいいのだが、大久保は泣けなかった。
だから、躯だけでも泣かせてやる。あの時代、兄が貴方をそうしたように、繰り返せばいい。
もしも体力が十分に備わっているひとなら、自分は彼が眠りにつくまでそうしただろう。望まれていようと、なかろうと。
「…できません、もう」
「――――……」
大久保は爪を更に立てた。これは彼の抱えた傷の痛みだと思った。
昔から従道は、本人が気に掛けない大久保の深い傷に心捕われてきた。恋とも言えるそれは従道の人生そのものでもあった。
どうすれば貴方を救える?
どうすれば運命は変われる?
「…壊れてしまいます」
「―――構…わない」
大久保の色褪せても尚紅い唇が小さく、だが血を吐くように激しく乞う。
構わない。構わないから、もう――――――
肉の落ちた腕が強く従道の背中を抱く。従道は、寄せられるままに彼に唇を重ねた。互いの絶望を貪るように。
歯列を割ってきた舌に自分のを絡めると自然に体が動いて、折角着せた小紋を太い指がやや乱暴に肌蹴る。再び始まった刻に、大久保は己から脚を開いた。
咆哮の闇に埋もれていくたびに従道を襲うのは、兄のかわりでもいいという切なさ。愛しいひとを抱ける至福。
もう構わないのは、自分もおなじだ。
馴らすために入れた指にさえ大久保は悦んで応え、きつく締め付けては奥へと誘い出す。頃合を見計らうことを忘れて指が抜き取られ、従道の猛りが大久保を穿った。
激情のままに体を進める。責められて泣き声をあげ続ける大久保を見下ろしながら、従道の脳裏に兄の顔が浮かんでは、消えるのだった。
どうすれば幸せに届くのだろう。貴方と兄はいつになれば。
――――答えははじめから、決まっていた。
たぶん、きっと、ふたりで死ぬときだ。
閣議が終了し、西郷の渡韓と大久保の敗北が決定した。
従道と大隈がいつものように大久保邸を訪ねると、待たされることなく大久保が奥から出てきた。二人の向かいに膝をついた彼の貌に、失望や疲労といったものは見て取れなかった。
これで吉之助さァを殺さずに済む。
それを聞いて蒼褪めた二人の前で、ひとり澄んだ目をして大久保は静かに微笑んだ。
