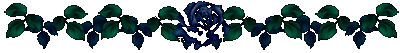
KAGEROU
あのひとは、髪を切った。
いつだったのかはわからない。私が邸を訪ねたときには、肩に触れるまであった髪の毛が項にかかるかかからないかの長さになっており、病的なまでに白い肌が剥き出しになっていた。
西郷翁が廟堂を去って数日、あのひとは会う度に蒼褪めてゆく。
誰にも心を許さないとでも言いたげに。
大久保が、はた、と硯に筆を投げ出した。折角書いた長い手紙に墨が散ったので再び書き直さなければならない。
「………」
くしゃ。
紙を掌で潰す音が夜更けの部屋に響く。
ここ数週間の疲れが原因で肘から先が強張って筆が震えてしまい、文字がところどころ判読不可能になっていた。大久保はそっと溜め息をついて傍らにある屑入れに投げた。
蒔絵が施された黒光りする文机に向かう大久保の貌は、ランプの灯りに燈されても尚暗く、一見すると現われていない苦悩が今にも浮き出そうだった。
部屋の隅に控える伊藤には長着を羽織っただけの薄い背中だけが見える。
一昨日、西郷が暇乞いにこの邸を訪れた。
辞表を出した。あとはお前に任せると呟いて。
それに対し、大久保は怒りを露にした。征韓論が二転三転したために衰弱したうえ寝不足の筈の彼が、カッと両目を開いて西郷を見つめた。
『もう、知ったこつか…っ』
あの声がまだ鼓膜に残っている。そのまま泣き出すのではないかと思った。
大久保と付き合うようになって数年が経過しているが、彼のそんな声を耳にしたのは初めてであった。だが、そんな大久保をみつめる自分の心に不思議と感傷は浮かばず、寧ろ更なる期待が頭を擡げていくのを感じていた。
このひとはやり遂げるだろう。胸に潜めた涙をも燃やして。
観測は希望ではなく、確信を含んでいる。西郷が大久保に国家を託すのも、自分と同じ思いがあるからだと思う。全く同じ情熱が、正反対の向きを目指している以外は、
(貴方がたはうりふたつだ。)
伊藤の脳裏に“愛憎”の二文字が浮かんだ。
「……」
外の空気が動いて振り返ると、夫人が小さく襖を開けた。来客らしい。
(こんな時間に、誰だろう?)
懐中時計は午前三時を指している。人を訪ねる時間ではないのだがこのところの騒ぎで、伊藤にも時間の感覚が喪失していた。
が、驚いたのは客の足音が客間を通り過ぎて真っ直ぐこの部屋を目指していることと、廊下を静かに進む気配に覚えのある匂いが漂っていることであった。
(薩人だ)
薩摩の人間は他藩出身とは異なり、日頃の様子は童子の如くに無邪気なものだが、何をかを決意してからは恐ろしいまでに颯爽としていた。己の命をも軽んじてその為に尽くす。このことは彼の仕える大久保にも言えることである。
襖を広めに開いて入ってきた客人は、やはり颯爽とした雰囲気を醸し出していた。
「失礼しもす」
夫人に案内されて部屋に入ってきたのは、永山弥一郎である。
大久保が小さく「あ」と言ったのが聞こえた気がした。大久保は永山を客間へ通そうとしたが、口を開く前に「ここがよか」と遮られてそれきり噤んでしまった。
思いがけない人物の登場に伊藤は一瞬体を竦ませたが、
(薩人は薩人同士だ)
と、ここは去るべきと判断し、手紙は後日受け取りに参ると大久保に言って、二人に頭を下げ部屋を出て行った。
「…どげんしたちいうとな」
伊藤の足音が廊下に遠く消えてから、永山に体を向けて膝を折った大久保が低く呟いた。
永山はすとんと畳に腰を下ろし、背後からランプに灯される大久保の貌を見た。
(眠っちょらんな)
彫りが一層深くなっている。一月程前会った時はまだ人間の色をしていたのだが、政務に取り掛かると時間と己を忘れ果てるのは昔から大久保の癖だった。
「髪ィ伸びもシたな」
鳶色のそれが大久保の肩に触れている。吸い寄せられるように体を伸ばし、永山は大久保の髪を掴んだ。大久保はびくり、と僅かに体を震わせたが永山のするがままに任せた。
男の癖に随分細い毛が、永山は好きだった。ふわふわと気持ちよくて、官人としての大久保の印象からは大きく離れていたが、この人物が実は痛みやすいひとであることを、永山は知っている。髪も躯も、細い。まるで大久保の真実を現しているようで。
…抱き締めたくなる。
「大久保さァ」
「……」
大久保は灰色の瞳を上げて、永山を見た。
永山はにっと唇を笑わせて言う。
「これを少し、おぃに賜はンか」
永山の言葉に大久保は一瞬、黙った。
彼でなくとも、髪の毛が欲しい、という科白が目の前の男――――永山は多くの薩人が憧れる第一級の隼人である――――の口から飛び出すとは予想しないだろう。
「賜はンか」
だが無邪気な顔をして繰り返す永山に溜め息をつくしかない。大久保は背を向けて文机の引出しを開け、取り出した鋏を永山に渡した。
永山は心底嬉しそうに受け取ると、立って大久保の後ろへ向かった。膝で立ち、鳶色の髪の毛…光を浴びてところどころ金色に見える…に優しく触れた。
そっと撫で付けて、鋏を入れる。
しゃき。
切ると、思っていた以上に軽い毛が永山の掌に零れてきた。その滑らかさに驚きつつ、切れ味のよい鋏の音に誘われるように永山は本題に入った。
「先生が故郷(くに)に戻られっと」
物音一つしない深夜の邸のなか鋏の音だけが繰り返され、応じた細い毛がぱらぱら落ちてくる。
「おぃも帰りもす」
「……」
大久保は沈黙したままだ。二人が顔を合わせても普段から会話らしきものは成立しないのだが、西郷が辞表を提出した今の状況からすれば、互いに相手が何を云いたいのか解っている。
薩摩へ帰るのか、政府に残るのか。
択一は、世界を背負った二人の人物のどちらに己の命を預けるか、に直結した。
大久保か。
それとも西郷か。
「おぃが東京に居ってもどげんもならん」
東京には、大久保の協力者が多くいる。川路がいるから大久保の身辺は心配ない。
東京を去るに当たって最も心残りなのは、大久保の精神であった。
数年前から、大久保の弱さを僅かながらも察することができる関係を永山は持っていた。尤も、啼くのは体だけで大久保が涙を流すことはない。一度もなかった。
迫ったのは永山が先だったが、意外にも大久保は大して抵抗しなかったのだ。それからは邸を訪れる度、大久保が眠るまで傍にいた。
幸せだと、おもう。
「よか土産ができもした」
永山は掌に受け止めた鳶色のそれを懐紙に包み、壊れないようそっと胸元に入れた。
肩についていた髪の毛が耳たぶのあたりで綺麗に切り揃えられ、年齢を感じさせない肌が白く透いている。月影のように清らかなそこに何度口づけたか知れない。
(このお人はあの頃から時を止めてしもたかも知れん)
京都。大久保と西郷が最も幸せを噛み締めていた時代。
どんなに焦がれても戻れない、遠い都。
ある意味で西郷はそこに戻ることを望んでいるかもしれなかった。だが、近代日本の建設事業に取り掛かっている大久保には過去など意味を持たないだろう。理性では。
本人の気付かぬうちに大久保の感情は悲哀となって彼の肌を傷つけ、血を流した。あまりの痛々しさに永山が、昔西郷がしたように大久保を胸に抱いても、虚ろな視線が宙を彷徨うだけで自分を見つめて微笑むことはなかった。
((西郷)先生ならどげんなさったじゃろ…)
永山には、大久保を抱き締めるしか彼を受け止める術を知らない。征韓論争論までは大久保と一対を為していた西郷なら、このひとの悲しみを癒しえただろうか。
…今の先生ば、とても無理じゃ。
結局西郷につく自分ではあるが、目の前であらゆる感情を細い躯のなかに押さえつけている大久保の姿を見ると、どうにもならぬ矛盾が生まれてくる。
(先生も先生じゃ)
今回のことで西郷は完全に大久保を棄て、近衛はおろか、ともすれば日本中が喉から手が出るほど祭り上げたがる体を、最も危険な桐野らに預けてしまった。永山は西郷派ではあったが、起きるであろう桐野らの暴発が目に浮かんで居たたまれない日々を過ごしているだけに、戊辰以来いわゆる西郷軍の将を務める自分までもが故郷に戻るのは、事態を更に悪化させるのではなかろうかと悩んだ。
が、決めた。
(もし俺が大久保さァの側に立ったら一層、先生はこのひとを本気で厭うだろう。それはいかん)
永山は西郷を守りたかった。
大久保も守りたかった。
せめてふたりの過去だけは、傷つけたくはなかった。
だから
(おぃは帰る)
と、今度は無言のうちに語った。
大久保は、永山を責めているようには見えない。
自分を責めているのだ。
(こういう御人じゃって)
そんなところも、大久保は薩摩にいた頃からひとつも変わっていなかった。西郷はしきりに腰抜けだのと貶したが、特に彼の貫徹さと創造力は日に日に成長している。
変わったのは、西郷の方だろう。あれほど熱中していた世治しから手を引いてしまったのだから。
(じゃっどん、先生が国を任せたんは大久保さァじゃ)
だから安心して政に専念していいのに、目の前で俯いて自分の膝を見つめる大久保は今回のことで殊更に深く傷ついているのである。
そんな彼を見るとこちらの胸も痛むのだが、もう決めたのだ。そう決心を繰り返した永山は大久保を励ますように、一層声を明るくして言ってやった。
「(西郷)先生は、おぃに任されっ」
暫く大久保は黙っていたが、やがて微かに首を横に振って小さく呟いた。
「…あんひとは逃げ足ば早か御人じゃ」
低い、聞き取りにくい声が今にも沈んでゆきそうだと永山は思う。
「おぃも負けもさん」
駆け足は得意じゃって。
剽軽めいて応えたが大久保は背を向けたまま雰囲気だけで、行くな、と言った。
永山は首を横に振る。
「大久保さァに代わって、面倒見っど」
センセイは手のかかる御人じゃぁ。
そう言って永山は静かに微笑んだ。微笑むしか、思いつかなかった。
永山の鼻から漏れた笑いに更に色を喪った大久保の背中を永山の黒い瞳がじっと窺っていたが、やがて両腕を大久保の胸に廻して薄い体を引き寄せ、
(もうお会いしもさん)
短くなった髪の毛の間から囁いて大久保を抱き締め、ランプの火を吹き消した。
(かぎろい(蜻蛉)じゃ)
組み敷く背中は薄く白く、障子に透けた月明かりのもとで更に映える。横顔を下に敷いた長着に伏せた大久保は、永山の体の下で甘い声を吐いた。
「ぁ……ぁ……」
肉が熱い。永山が揺れる度に体を強張らせてうめいてはきつく締め付け、穿つ永山を悦ばせた。だが体力の衰えた体を酷使することは出来ない為、組み敷いて攻め立てるのは止めて、自分を一度抜いて大久保を仰向かせ、再び大久保の中へ戻る。
「…ひ…っ!」
大久保の下腹で跳ねるそれをそっと握り、一層深く腰を押し付けて、もう少しと囁き白い項に口づける。その間にも大久保は永山の掌のなかで泣き、腰を振って解放を求めた。その姿に胸の奥深くに沈めていた激情を掻き毟られて、永山は両手を冷たい腰にあてがい、一気に体を進めた。
声にならない叫びを上げて大久保が啼いて、果てる。ぐったりと永山にすべてを預けて眠りについた。
その顔を見ると、これが平素のあのひとだろうかと疑うような穏かで無垢な貌。
ああ。
やはり蜻蛉だ。
儚そうに見える体に、数え切れない未来の種を宿している。時が過ぎるたびに肢体は薄く透け、宿した未来が見えるのだ。
あなたはすべてを為すだろう。
呟いて、永山は頭を上げた。
障子から朝の光が差してくる。これから訪れる希望のように、それは優しく永山を照らした。
「夜明けじゃ」
そう言って眠る大久保にそっと口づけて、別れを告げた。
胸から取り出した懐紙には、鳶色の髪の毛が丁寧に包まれている。ただし切った髪の半分は、大久保が薩摩の土を踏むことはないだろうからと、薩摩を出るときに風に吹かせて飛ばした。
残りは、
(おぃと来て賜ンせ)
髪の毛から香る薄い香りにふっと頬をほころばせ、髪の束を摘まむとそれを火の中へ投げた。音を立てることなく一瞬で燃えたそれを眺める永山の胸に、人生が夢のように去来する。
過ぎてしまえばなんと儚い日々。それもすべてこの戦で消えていった。
だがあのひとが新たな世界を創るだろう。払ったすべての犠牲に換えて、彼にしか創りえない輝く未来を。
夜明けを、俺は信じる。闇は早くに去るのがよい。
永山は一度目を閉じて短刀を鞘から出して握り、瞼を開けて一気に腹を掻き切った。
焦げた天井が支えを失い、視界がかすむ永山の周りへ次々と落ちて火の粉を降らせた。腹から飛ぶ血飛沫が燃え上がる炎へ昇華してゆく。まるであのひとと過ごしてきた動乱のようだと思った。が、自分は死に、彼は炎を越えて生きるだろう。
翔べ。愛しいひとよ。
我等が死ねば、一挙に貴方の夜が明ける。
熊本南郊が落ちたという電報が京都旧御所に入ったとき、大久保はひとりで部屋にいた。政府軍に追い詰められた永山は、民家に火を放って自害したそうだ。彼のことだ、死ぬためだけに大金を払って家を買い、ひとり果てたのだろう。
大久保は人払いをして、薄暗い部屋に篭った。
『かぎろいじゃ…』
最後まで明るく、だが哀しげにそう囁いた声が、まるで昨夜のことのように鼓膜に蘇る。
『大久保さァ、日本の夜明けは間近じゃ』
創って賜ンせ。
突然、深く澄んだ声が耳の奥から響き屈託のない微笑が脳裏に浮かんで、大久保は自分の胸が痛んでいることに気が付いた。不意に、瞼が熱くなる。
あの鼓動はもうない。夜明けの如き眩しさも、優しさも。
(…永山)
蜻蛉は、夜明けとともに死ぬんじゃ。
溢れた涙がこけた頬を伝って、膝の上の鋏を温かく濡らした。
