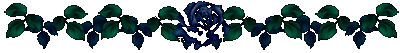
HOTARU
時折あのひとを襲う激情というものは、到底あのひと自身抑えきれるものではなかった。年若い頃西郷と刺し違えて死のうとしたことがあると聞いたときは、そんな馬鹿げた喋(はなし)と高を括ったものだが、征韓論一派が一斉に帰郷してからのあのひとの様子を目にすれば、私でなくとも「それ」が何を意味するか分かり得ただろうと思う。ましてそれが、あのひとの周りにいた人間なら。
「……」
今日も東京は一日中雨である。
蕭々と降り続き、白い頬を密かに伝う涙の音を掻き消してゆく。
往時あのひとの躯を抱いて受け止めた、毅(つよ)き麗し義侠の如く。
このごろ帰宅すると、桐野が断りもなしに家の縁側に腰をかけて庭を眺めているのが目に入るようになった。
「早いもンでごわすなァ、蛍ィ一匹も出もはんど」
白い歯を出して笑ったが、桐野の逞しい体からは普段発せられているものとは異なる雰囲気が混じっているのが感じられた。
殺気ともいう。
知らぬふりをして俺は奥へ行って制服を脱ぎ、絣(かすり)に帯を廻して一度顔を洗い、それを肩に掛けた手拭で拭いた。その頃、桐野は既に持参してきた焼酎を茶碗に注いで飲み始めている。俺も彼の隣に行って胡座し、もうひとつの茶碗に注いで飲んだ。
庭から鈴虫の鳴き音が聞こえる季節である。
「つやつや光る女子な尻見とうて来たちゅに、一匹も出んとは寂シこつでごわす」
この屋敷の庭に出る蛍を見に来るのが、桐野は好きだった。暗い闇のなかほつりほつりを灯っては消える頼りない虫が、頼りなさとは無縁といっていいこの男の趣味と知ったときには思わず噴出してしまい、それが桐野の本格的な怒りというか照れを買って以来、この男は俺の前ではすっかり開き直ったか、蛍を眺めるだけでなく庭に咲いている草や花を千切っては遊びするようになった。今も彼の膝の上には龍脳菊と竜胆が一輪ずつあり、それが金モールに飾られた軍服に良く映えている。
桐野は湯飲みに残った焼酎を、一気にぐっと飲み干した。
それでも両目は座っている。軍服をいまにも引き千切って暴れ出しそうな精気を孕(はら)んだままで、桐野は本題に入った。
「太政官が割れちょる。征韓論じゃ。西郷(せご)どんな言わるるは、義を以って韓を治め、オロシヤを攻める。俺は西郷どんの護衛も前衛も務めッつもりじゃ。…どげん思うちょる。不賛成か」
「――――んにゃ(=でない)」
俺が答えると、桐野は膝の上の草花を取って勢い良く庭に放り投げた。反対だと言えば、この男の銀剣が俺をまっ二つに斬っていただろう。その刀を床からひっつかんだ桐野は縁側から立ちあがり、靴を脱いで居間に上がった。
「篠原さぁ。祝杯をあげもそ」
程よく酔い、桐野が帰った後、俺は胡座をかいたまま縁側で暫くぼんやりしていたが、月明りひとつない視界の端に懐かしいものが映ってはっとした。
蛍だ。
ゆらゆら揺れながら、二つの灯(ひ)が互いに円を描いて飛んでいる。
「……」
それを見ながら、俺は遥か昔のことを思い出していた。
表に出ると、普段居るはずの誰かがひとりも居なかった。暫く探し回ったが、やはりみつからない。仕方がないから、俺は今日はひとりで過ごそうと思った。
履き慣れた草鞋でずんずん歩く。ひとりでいるのは嫌いではない。どこまでも青い空を我が物顔で支配する入道雲を追いながら、小高い丘を登り、駆け下りて、草叢で跳ねる虫や蛙を掴まえる。それに飽きると河原へ行って褌(ふんどし)一丁で泳いだり、浅瀬に入り腰を屈(かが)めて小石をひっくり返して石の裏にへばり付いた幼虫などを眺めた。
そうしてふと気がつけば、真上からじりじりと照り付けていた日光はとうに西に傾き、真っ赤な残光が俺の頬を染める時刻になっていた。
俺は河川敷に畳んであった単衣(ひとえ)を着、草鞋を履いて歩き出したが野山を散々に駆け回った所為で鼻緒が今にも切れそうである。生憎手拭など何も持ち合わせていなかったから、歩いては時折屈んで姿勢の悪い鼻緒をいじり、また歩くという動作を続けた。
随分遠くまで来ていたらしく、まだ城下の明りも見えぬというのにすっかり日が落ちてしまった。こんな場合幼いというのは不便なものだ。豊富な雨と日光に勢いを得た草が背丈をぐんと伸ばすから、小さい俺など完全に隠れてしまう。俺は猛々しく茂る草叢の中、草が無くてそこだけ取り敢えず道になっているところをとぼとぼと歩くしかなかった。流石に心細かった。
―――――と、そのときである。
俺の視界の右斜め前辺りで、突然ガサッと音がした。
「!!」
不覚にも驚き、俺は尻餅をついてしまった。
「うわ…!」
珍しく声が出た。その声で先方も驚いたらしい。ガサガサという音が大きくなって俺に近づいてきたと思ったら、草の間からひとりの少年がひょっこり頭を覗かせたのである。
「あ…」
そう言って少年は尻餅をついている俺に寄ってきて、道に膝をついた。
「驚かせてしまったようだ。ごめんね」
声変わりし始めの、甘い声音だと思った。
「大丈夫かい? どこか挫(くじ)いた?」
少年は必死に問い掛けてきてくれるのだが、俺は月光を浴びた少年の貌に見惚れてしまい、ふるふると首を左右に振るしか出来なかった。
「そう…じゃぁ、立ち上がっても平気だ」
少年は尻の後ろについた俺の手をそっと掴んで、ゆっくりと俺を立たせた。立つと、少年が年の割に上背があるのが良く分かる。そのまま手を繋いで、俺立ちは歩き出した。
が、道の両脇に茂っていた草叢が途切れたところで、少年は俺の手を引いて甲突川のほとりに俺を連れて行く。
川面にゆらゆら揺れて見えるのは月だ。その明りが、少年の動作を俺に教えてくれる。
少年は袂(たもと)からきちんと畳まれた手拭を取り出しておよそ三分の一のところで引き千切り、大きい方を川の水につけた。何をするのだろうと見ていた俺の前に来ると、布切れになった手拭を軽くしぼり、俺の頬や額を丁度良い加減で拭き出したのである。
そういえば昼飯を摂ってからの俺はあちこちの山を駆け、水浴びをしたといっても泳いでいる魚を手掴みで取ったり川の砂を掘ったりしていたから、顔じゅう汗と泥だらけだったのだ。それに気づかないでいた俺も俺である。俺は顔から火を噴出しそうになった。
静かなまま少年は川と俺の間を何度も往来し、着物からはみ出た首や腕を丁寧に拭いている。火照った体に川の水はとても心地よく感じられた。
しかし、
「……」
水よりも更に少年の掌のほうが俺には快かったのだ。ひやり、というよりもしんと冴えた冷気とでも表現したほうが相応しいに違いないだとう白く澄んだ肌が、俺から熱を奪っていく。なのに俺は、一度も嫌悪感を抱いたことはなかった。
「……」
俺の肌を拭き終わると、彼は俺の草鞋を脱がせ、ぼろぼろになった鼻緒を残りの手拭で作り直した。
「…さ、行こう」
彼は再び俺の手を取って歩き出した。
俺は少年が大久保一蔵であることを知っていた。「あの」郷中頭の西郷さんの幼馴染だということも知っていた。
西郷吉之助は城下で最も名高い徳者だ。彼のまえにひざまづくと喜びで体が震えると聞く。声を掛けてもらうだけで心の臓がはちきれそうだという。
一方で大久保一蔵と言えば一個独立していて、どうにも近寄れない。なのにこの二人が根っから分かり合っているのが解せぬ、という会話を俺は毎日のように耳にしている。
でも俺はこのひとが嫌いではなかった。
「……」
大きな手。白い頚。蒸すような夜風に吹かれる鳶色の髪の動く速さは最初からきっちりと、幼い俺の歩調に合っている。
俺は相変わらずの無口のまま彼に凡てを預け、背に月光を浴びながら真っ暗な小道を進んでいった。
するとやがて、視界の隅でふわりと何かが浮かび上がった。
「……、」
俺は足を止めた。すぐに、彼も止まった。
「どうしたんだい?」
いまにも闇に溶けていくような静かな声で訊いて来た。
俺は彼の冷たい温もりを小さな掌いっぱいに感じながら、声を出した。
「…いま…」
「うん?」
彼が応答してくれたときだった。
月に雲が掛かった。合わせて俺たちの視界も閉ざされる。思わず息を潜めたが次の瞬間、真っ黒い空間に一斉に小さな灯がついたのだった。
俺は声を出していた。
「わぁ……!!」
幻など信じない性質(たち)であったが、このときばかりはそういう非現実に身を浸しきりたいと願った。
「…すごいな…」
彼も驚いたようだった。
灯りは当初は互いにバラバラに光っていたが、次第に点滅の間隔が揃って空(くう)を移動しながらも一斉にふわりふわり灯るようになった。
常に移動してしまう対象に対し、どこをどう見たら良いやら分からなくて、俺は彼を見上げた。すると彼は光ではなく、空間そのものを眺めているように見えたから、俺も真似して彼と同じ方向をみた。
そのぐらい経った頃だろう。
「…蛍はね、」
と、彼が喋り出した。蛍の散飛を邪魔せぬよう気をつけたような穏やかな口調だった。
「蛍がこうして生きるのは僅か数日のようなんだ。そのうちに相手を見つけて交尾をし、卵を産んで死んでいくんだ」
「…数日?」
「そう。だから明日には、彼らは草の上で屍になっているかもしれない。…でもきっと満足だろうな。好いた相手と一生を添い遂げられるのだから。虫の世界にも夫婦(めおと)があると思うよ」
「……」
「違うかな」
「……」
俺は考えていた。いろいろと。俺のこと。両親のこと。遊び仲間に西郷さん、そしてこのひとのことを。
今思えば、大久保さんの台詞は幻想的な風景に驚嘆している子供に聞かせるべきものではないのだが、あのときの俺はそんなことは感じなかった。口下手な癖にまるきりそれを忘れて、気がついたときにはかなり大胆な台詞を口に出していたのだ。
「おぃは大久保さぁと夫婦になる!!」
喋った、というよりも叫んでいた。まっすぐに彼を見上げながら。
「夫婦になってずっと一緒に居(お)るンじゃ!」
彼ひとりを、みつめながら。
俺の叫びに応えたかのように隠れていた月が顔を出した。そして彼を照らしていく。
白い。
綺麗で透明で、強そうでいて儚くて、細い躯は今にも折れそうで、灰色の目はどこまでも澄んでいて―――――――…
大久保さんはその目を大きく開いて俺を見下ろしていた。普段全くといって良いほど無口な俺から出たのがあんな言葉だったからさぞかし驚いたことだろう。そうして彼が自分の為に驚いてくれたことすら、俺は嬉しかったのだ。
独立しているようにみえてその実西郷さんに護られていて、すれ違うだけで手の届かぬひと。颯爽と歩く後ろ姿を、いつも俺は探していた。見つけたと思ったときには西郷さんが隣を一人で占めていて、ただでさえ年の離れた俺は近づくことすら叶わなかった。
その彼が、こうして自分を見つめてくれる。手を繋いでいてくれる。だから二度と、離れたくなかった。
「…お、おぃは、おぃは……」
あまりにじぃっと見つめられているうちに、余計な感情とは嫌なものだ、照れ臭いという思いが芽生えて来て、折角の口上もここまでになり、いつもの癖(へき)で俺は口篭もってしまった。
一度そうなるともう意味をもつ言葉というのは出てこない。あ、とか、う、とかいう音を発声するにも照れてしまった俺は、先ほどまでの勢いは何処へやらで、しゅんと俯くしか出来なかった。
そんな俺に注がれるのは、周りの人間が争って罵る棘のような視線ではなく、柔らかな淡い眼差しだった。胸が竦んだ。
「…夫婦は男と女がなるものだよ。君と俺では、難しいかな…」
彼の口から出たのは当然の摂理である。
当然だ。そんなことは分かっているのだ。
俺が、俺が云いたかったのはそうではなくて――――――…
俺は、大久保さんと繋いでいるほうと逆の手でぎゅっと握り拳をつくった。小さな体が震える。きっと、彼にも伝わる。
俺は震える心のまま、再び唇を動かしていた。
「嫌じゃ。おぃは大久保さぁがよか」
蛍の光が彼のこけた肌を照らしてゆく。ああ気がつけば、俺たちはずっと立ち止まったままなのだ。幻想的な闇にふたりきり、途方も無いことを喋り続けている。だから俺は必死だった。
ここで御座なりにするのは、嫌だった。
「おぃは大久保さぁが…」
俺の拙い言葉を、大久保さんはゆっくり待ってくれている。
あの眼差しの深かったこと。
「大久保さぁが…」
そこまで来て彼の視線が一段と深くなった。決して恐怖を覚えはしない、穏やかな、そう、こんな蛍に灯される夜のような静けさ。
この「夜」に溶けこんで、ずっと満たされたかった。
「…ありがとう」
大久保さんが答えた。
「君と夫婦にはなれないけれど、毎年こうしてふたりで蛍を見に来る約束をしよう」
「…ふたりで?」
鸚鵡返しにした俺に、大久保さんは少し笑った。
「そう。ふたりきりだ」
「……ん…」
嬉しくて俺は、大久保さんの手をぎゅっと握った。
そうして歩き出す。ふたり歩調を合わせながら、群がってくる蛍の光の散舞のなかを、少し高揚した気持ちのまま過ぎていった。
六日に開かれた寄合(よりあい)で出兵が採決されても猶ひとり家に篭って顔すら出そうとしない永山を、桐野が欲しがった。
永山には将器があり、また仁徳がある。公の場で堂々と出兵反対の義を唱えたこともある。その永山を兵営に加えるということは、元々政府の側にいて私学校についても一歩引いて冷静に見ていた人間までもが、(西郷)暗殺団を仕向けてきた政府の挙動に不満憤怒していることを指し、政府を糾弾、攻撃することへの適切かつ痛烈な意義を与える。
だから永山は外せない、この詰めは外せないと桐野は豪語していたが、数回足を運んだ割に収穫は無かった。
妻に少し出てくる、と言って俺は家を出た。
暫く歩くと、やや消沈した桐野に出くわした。
「…駄目じゃ、永山さぁは駄目じゃ。あげに重ぅては営所に連れるにもひと苦労じゃ」
赤銅色の頬を緩めた桐野だったが、それは苦笑いにしかならなかった。
桐野は来た時のまま、肩を落として帰っていった。
俺は永山の家へ入った。
「俺じゃ」
言うと、永山は憮然とした表情で俺を殆ど睨んできたが、一応居間に上がるよう口を開いた。勧められるまま、俺はそこへ膝を折り、話しだした。
「俺は昔、親父にも誰にも秘密にして甲突川河川敷に大久保さぁと蛍を見に行った」
ぴくり、と俺の背後の気配が揺れた。俺の膝の前に出された湯飲みが、床にこつりと当たる。
「雨の日を除いて毎日、あンひとが鹿児島(かごんま)ィ居るときは毎年な」
手をつないで。
幼い子供のように無邪気のまま、草叢を転げまわった。俺のほうが背を越してからは、あの白い肌を噛んだりして。
「……」
永山は俺の真正面に正座した。俺の喋(はなし)の真意を探ろうと床をみつめ、じっと耳を傾けてくる。
「西郷(せご)さのつけた痣ァ見っ度、悔しゅうての。俺も真似したもんじゃ」
と言うと、ぴくり、また永山の瞼が動いたのが分かった。俺は畳みかける。
「蛍ば見っときは、大久保さァは俺のもんじゃった」
「……」
それがどういうことか永山に分からぬはずがない。永山は、俺と同じ類の人間なのだ。その永山は、それまでのしぃんとした雰囲気を一気に変えて、体じゅうの毛を逆立てる猫のように俺に食ってかかってきた。
「その大久保さぁを討て言ったンはおはんじゃろうが篠原さ!!! 立ち上がったら引き返せん! 皆が死ぬるまでこの戦(ゆっさ)は終わらんど!!」
あのひと死ぬまで、終わらんど――――――――
飲み込んだ永山の声が聞こえる気がした。或いはそれは、俺の叫びだったかもしれない。
俺は永山の気持ちを知っていた。薩摩が蜂起すれば政府への痛手が凄惨になるだろうことも知っていた。
だからこそ俺は、永山に言わなければならなかった。
「聞け、永山」
俺は永山の視線を捕らえた。
「何じゃっ!!」
血走った目で、永山が俺を見る。
俺は言った。
「永山、おはんな勘違いしちょる。俺が挙げるンは政府でも大久保さぁでもなか、西郷さぁの御首じゃ」
声に出した瞬間、目の前を、さぁっと風が吹いたように思った。
靡(なび)く鳶色の髪が目に浮かぶ。その隣を歩いていたのは西郷さんだ。夫婦よりも、深い仲だったのだ。
そのふたりが乖離したのは、遥か昔にも、昨日のことにも思える。
大久保、西郷、大久保、西郷、大久保、……
この両者が激突するのはもはや自明の理である。戦が起こればひとりが勝ち、ひとりは負ける。
俺が東京でみたもの。着々と軍備を整え、大勢の薩人が脱隊したところで、職にあぶれた士族らが群がり軍隊は益々強化されるに加えて、西洋式の武器弾薬を豊富に作り出す機械も技術も合わせもっている。
よって俺たちは負ける。西郷は負ける。しかし西郷が無くても、国には正規軍が残る。余計な戦力が無いほうが、あのひとの政府は政府たり得るのだ。
だったらいっそ――――――…
「……ッ」
永山が泣き出した。
膝の上の握り拳のうえに透明な涙が零れる。零れては、着古した薩摩絣に染みていく。
俺がそれを目で追ううちに、永山は声を上げて泣いた。俺は黙って、永山の声を聞いていた。
『片方の蛍が早くに死んだら、残ったほうはどげんなる?』
幼い俺の声がきこえる。そしてあのひとの答えが蘇った。
『そうだな、きっと新しい相手を見つけるんだよ』
あのひとの傍らには、光る輩が大勢居るのだ。だから、
西郷さぁ
あンひとのために、死んで賜はれ
