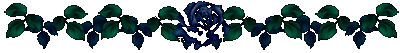
Koyoi mo Imachi ni Souraeba
酷い頭痛がして目を開けると、視界は酷く暗かった。
体中が鈍痛に悲鳴を上げている。ここは浄土かはたまた地獄かと侭ならむ頭脳を巡らせていたが、燻ったような香の香りが鼻をついて、終に極楽へ至ったかと思った瞬間、がらりと障子が開いて、夜風が俺の褥(しとね)を湿らせた。
現われたのは、闇にも映える月光の肌。彫りの深い貌に埋め込まれたような瞳はぎらついて、幼子には似合わぬ光芒を含んでいた。
「和尚」
総髪の、まだ十を越えたばかりにみえる童は、声変わりする前の澄んだ声で廊下の向こうを見やった。やがて、奥からぱたぱたと小走りに掛けてくる足音が聞こえて、どうやらここが楽獄のいずれでもないことを俺に示唆する。
「和尚、起きたぞ」
「おお!」
近づいてくる坊主の明るい表情をみながら、俺はもう一度瞼を閉じた。
広いとは言えない境内には、まだ弥生の初めだというのに見事な桜が咲いている。隣には見たこともない植物が茂っており、ここが南国であることを噛み締めさせられた。
庭石を敷き詰めた境内では、痩せた童と対照的に肥えた童とが木刀をもって組み合っている。
痩せた方の棒のような腕だけをみれば如何に示現流と聞いたとて怖れ様もないのだが、発する気の強さは何事だろう。加えて、もうひとりのほうの重量としか表現できない存在感。
あんな童が屯(たむろ)する土地に流れ着いたのだ、とんでもないことをしてしまったと、今更ながら己の所業に呆れていた。
「…御迷惑をお掛けし申した」
頭を下げると、住職はいやいやと人の良さそうな老顔を綻ばせながら、肩袖を左右に振った。
「なんのなんの、若き御仁を御助け下さったのは御仏の御計らい。御気に為さらずゆうるり養生なされ」
「……忝(かたじけな)い」
再び頭を下げると、住職はそんなこと、と再び袖を振った。そして視線を境内へやって、童を呼んだ。
「吉之助、正助! 御客人の御耳に障る!!もう少し大人しゅうできぬのか!」
途端、それまで続いていた組打ちの音は止んで、太った童がこちらに深く礼をした。が、もうひとりは
「……」
俺と視線を合わせるなり木刀を目の前に放り投げて、すたすたと境内を俺の目が届かぬ所へ歩き去ってしまった。
「正助!」
振り向きもしない。
からん、と捨てられた木刀を拾い上げ、肥えた童が追ってゆく。童といっても立派な容貌と体格を持っており、他藩で見かける聡明さだけを全面に押し出した子らとは雰囲気が大きく異なっていた。
俺には、二人が境内の端に消えるのを呆然と眺めるしかない。
「…やれやれ」
と和尚は息をつき、褥に体を起こす俺の肩に長着を掛けた。
「今に食事をお持ちしましょう。こんなところですから、菜しか揃いませぬが」
穏かに笑って、和尚は廊下へ去る。まだ年若い俺に精進料理は合いにくいと思ってのことだろうが、俺はそんなものなど食べなれていた。
京を離れて十日経た頃、摂津から出る船を乗り換え乗り越えして南街道を歩き、土佐まで着いたまでは良かったものの、そこで意気投合した漁師の船に乗せてもらって、黒潮を渡ってみた。が、途中嵐にあって船は難破し、目が覚めたらここに寝ていたのだ。
介抱されて幾日過ぎたのか分からないが、体はすっかり温まり、別にどこを動かしても不自由はなかった。林に囲まれた境内に訪れる者もなく、俺は追っ手を気に止める心配もないまま、ゆうるりと静養に預かっている。
が、信じられないのは、この地が質実剛健で名の知られた薩摩であるということ。完璧な封建社会のもと、部外者の侵入を険しい山地とその慣習で断ち切り、見つけようものなら何をされるか分からない。中央の制度など、ここではなんの意味も持たなかった。
…やはり俺は、突き放される運命(さだめ)にあるのだろうか。
儚いまま、――――このまま、現(うつつ)に埋もれてしまえと?
「愚かな……」
何が悟りなのかと、長いこと考えてきた。仏になるため、極楽へ昇る為。
…それもよかろう。しかしそれでは現(うつつ)を救えない。経を唱えたところで世界が変わるはずがないのだ。救われようものなら、銭や病に苦しんで死ぬものなど、存在できないだろう。年を食って周りがだいぶ見えるようになった俺は、何もしないままでいることこそが地獄だと思うようになっていた。
立場上、俺の激しさを戒める者はいなかったが、あの建物のなかでまさかこういうことを口にするわけにもいかず、弟へ手紙を残した。そして出てきた。住み慣れた畿内を遠く離れ、俺はこの地へ至ったのだ。
しかし、あろうことかここは薩摩。現だの地獄だのという暇(いとま)を感じる余裕は恐らく今ぐらいしかなく、全快したら城下で厳しく裁かれるか、その前に消されるかだろう。
「……」
俺は頭を抱えた。
これでは世を救うどころか、救われる可能性すら見出せないではないか。このさきどうすれば…
そこで俺の思考が止まった。
何故、助けられたのだろうという疑問にぶつかったから。
「……」
匿っているのが藩に知られでもしたら、如何に僧都だろうと罰されるだろう。酷ければ獄舎で死ぬことになるかもしれない。なぜ住職は、そんな危険を冒してまで俺を介抱したのだろうか。
なんということだ。世を救いたいと望んで旅にでたというのに、穏かに暮らしていたひとを突き落とすなど。
…やはり俺はどうしようもない愚者なのか。気性の激しさを押さえることすらできずに、ひとを不幸にするだけの…
「お待たせし申した。どうぞお上がり下され」
声がして、はっと頭を上げると、和尚が飯や菜の乗った懸盤を持ってきた。有り難いことに櫃(ひつ)まで揃っている。薩摩は米の余り豊富ではない土地と聞いていたが、立派な白米が俺の体調に合わせてか、いささか柔らかめに炊かれていた。
深く礼をして、俺は箸をとった。
和尚が言うには、この飯は先ほど正助、と呼ばれていた童が炊いたものだという。城下で城下士に酷くいたぶられると、この寺に来て幼馴染の吉之助と組打ちしたりしているそうだ。
正助は昔から体が弱く、屈強で知られる薩人の血が入っているとは思えないほどか弱い印象を受ける。色も白く、毛髪は細くて頼りない。身分の違いも相まって城下士の格好の標的になるらしかった。
尤も、俺のみたところでは、そういうのだけが原因であんな容貌になったとは思えないのだが。
俺は思い切って尋ねてみた。
「何故拙者を助けて下されたのです」
「……」
「貴方がたにとっては、ご迷惑になるだけでしょう?」
「……」
俺の問いかけに、和尚はふ…っと微笑んだ。意外な表情をされて、俺は戸惑う。
和尚は、いつのまにか戻って来て庭に足を投げ出すように簀子(すのこ。縁側)に腰掛けていた正助たちを見やった。
彼の顎がゆっくりと上下する。
「貴殿を見つけし申したのは、あの正助でしてな」
「……」
「…あれの目に止まったものは、不思議なことにやがて大きな芽を吹くのです。その正助が貴殿を見つけ、介抱し申した。拙僧はあれの手助けをしたのみです」
和尚の声がこだまする。それが乾いた心に染み透るのを感じながら、俺は鳶色の髪の毛が風に柔らかくなびくのを見ていた。
南国とは言え、病床にある者にとって夜は若干冷える。俺は和尚に借りた十徳(じっとく)を羽織って脇息に寄りかかり、夜空を眺めていた。夜気はどこでも澄んでいるものだが、ここの眺望はとりわけ素晴らしい。無駄なものは一切存在させない薩摩の風土のなかで、玉を散りばめたように星々が瞬くのは、暗澹たるこの国に埋もれた逸材の放つ才のようで興が惹かれ、俺は飽くことなく簀子に座って空を見上げている。
開け放たれた障子の向こうから聞こえてくる足音さえも伴奏にして。
「病人は早う眠れ。そげなこつ、子供でも知っちょるぞ」
「…お前も子供ではないか」
正助、と言うと背後がはっきりと殺意を帯びた。不覚にも、鳥肌がたった。
「外見に反して、そういうところは流石薩人だな」
「煩か!」
正助はどかっ、と細腕に抱えていた掛け布団を床に叩き付けた。俺の尻までが揺らいだくらいだ。
そのくせ正助は立ち去ろうとしないのだ。気が収まってもそこに佇んで、暗闇で目を凝らしている。ふつふつと闘志に近いものを全身に漲らせて、状況はそこまで体を張るものではないのだが、彼から発せられる後光のような威厳を俺は感じた。
「…星、一緒にみるか」
さりげなく誘ってやったのに、
「そこは俺の場所じゃ」
と正助は事も無げに言い放つだけだった。
…可愛くない。
俺は本当にこれに命を救われたのだろうか。
「お前、いつもそうなのか。城下では城下士に散々なめに遭わせられておると聞いたぞ」
年端も行かぬ子供に対するにしては言葉が過ぎるかと我ながら呆れていたが、俺は問い詰めるようにして正助に向き直った。厳しい視線を作って、さも真剣であるかのように振舞う。
相手がこう挑めばこの童はこちら以上の真剣さを以って返してくることを、俺は悟っていたのかもしれない。或いは、そうなるように強制したとも言えるのか。
本性を曝け出させるために。
「……」
案の定、正助はぎりりと奥歯を噛み締めて、真っ直ぐに俺を睨んできた。その険しさに制御が追いつかないのだろう、蒼褪めた肌まで震えさせながら小さな体を昂ぶらせ、いまに鳶色の髪の毛がゆらゆらと靡(なび)き出すのではないかと俺が身構えるほど、それは極上の光景だった。
こちらの思考など鼻にもかけずに正助のやたらと紅い唇が動きだすのを、俺は見ていた。
「城下士じゃろうが郷士じゃろうが、…踏みつけられようと、俺は俺じゃ。流れ者のお前に言われるこつじゃなか」
が、彼の声は俺には無機質で意味を為さない。或いは俺以外の何者かが俺にそうさせているのではないかと思うほど己の感覚が麻痺し始めているらしいと、残った理性が叫んでいた。その理性すら、確かな狂気を帯びて飲み込まれていく。
絣(かすり)から覗く棒のような脚はこの暖かさだというのに蒼白く、上に立つ彫りの深い貌は真実血が通っているのかと疑われずにはいられぬほど透いている。窪んだ眼窩に埋もれた瞳は灰色で、言い知れぬ闇と―――――いまは悔しさと失望に汚れているものの、やがてその汚れすら払拭するであろう光を宿していた。
ほんとうに子供なのかという疑念は既に無い。あるのはただ、憤りに似た興奮だった。
「なぜ俺を助けた?」
俺は問うていた。
「ともすれば罰せられるだろうに」
言うと、正助はぐっと白い歯で下唇を噛んだ。罰せられることの意味を分かりながらも、俺を助けたというのか。
和尚の声が蘇る。
『あれの目に止まったものは、不思議なことにやがて大きな芽を吹くのです』
もしもこの俺が生き残ったことが正しいなら、そのわけを教えてくれ。
「…来い」
俺は両腕を十徳から出して正助のほうへ向けた。果たして、正助は素直に応じてこちらに歩いてくる。
見目にも細い躯を抱いて、膝の上に座らせた。一蹴りぐらい覚悟していたが、そういった衝動性は見せずに大人しく俺の膝に納まる。やや安堵して、俺は体を反転させて簀子に胡座をかきなおし、庭を向いた。
体を支えてやると大層痩せている。肋(あばら)が浮き出てひとつひとつなぞれそうだし、やたら温度が冷たいのが意外だった。子の体温というものは成人のそれよりも高いはずなのだが。
痩せているから、軽い。その軽さに、俺は昼間見たもうひとりの童を思い出した。
「昼間、お前と組み打っていた童は、お前の兄者か」
ぴくり、と正助が反応した。尤も、俺は二人の間柄が兄弟でないことは和尚から聞き知っている。
「兄か?」
「違う」
「ならば、朋か」
「……」
正助は黙った。じっと暗い庭をみつめている。否、みつめているのはその奥に拡(ひろ)がる眩い虚(そら)かも知れなかった。
「どうした」
「……」
「兄でも友でもなければ、なんなのだ」
「――――俺の…、太陽じゃ」
生温い風が吹き、正助の細い髪の毛が揺れる。俺の胸に、彼の薄い香りが届いた。
「お前を助けたのも、見過ごせば吉さぁが嘆くと思ったから」
優シひとじゃ、と正助は続けた。
「優シ過ぎてどげんもならんときもある。じゃっどん、俺はそげん吉さぁが…好きじゃ…」
「陽のように、温かいか」
「じゃ」
「お前は随分冷えているから離れられないのだろう」
冗談で無く、正助の体は冷え切っている。風呂上りでしかも南の夜だというのに、着物の上からはっきりと感じるほど、正助は冷たかった。
白く冴える光はまるで。
「正助」
「?」
「太陽がなければ、俺たちも植物も生きてはいけない」
「じゃ」
「お前、吉之助は太陽だと言ったな」
「…じゃ」
「あいつは世のなかの太陽たり得るか。日本を救う、明かりを灯すか」
子供に尋ねるものではないが、そんなことはどうでもよかった。
世は乱れ、徳川に力はない。今に戦国宛(さなが)らの群雄割拠、或いは外国による割拠が起こる可能性すら薄くはなかった。追い詰められた民の心は荒れ、やがてこの世が地獄と化すだろう光景は、決して現実化してはならぬもの。望むべきは、叶うべきは極楽たる世なのだ。
遥かなる浄土を目指して生きてゆくのだ。
「もう灯しちょる」
正助は即答した。俺の出した抽象的な問いに対し落ち着いた声できっぱりと言い放つ様子は、太陽だという吉之助の隣にいるに相応しい大人のそれであろうと思われた。
もし、このふたりが世を立て直すとしたら、どうだろう。その考えに至った俺は、船が難破しても生き長らえた理由を見つけ出せた気がした。
或いは…或いは、これが“悟り”かもしれないのだ―――――…
となれば、俺が為すべきことはひとつ。だから続けた。
「月は、太陽の光を浴びてあのように輝くのだそうだ。そして太陽は月を追いかけている」
「知っちょる」
「ならば正助、お前が月になれ」
「…!」
「―――そして吉とふたりで日本を照らせよ」
言うと正助は腕のなかで震えた。俺の科白に童子らしく全てを受け止め心をうち震わせているのか、強い視線で星空を、そしてそのなかで第一等に輝く月を眺めて感慨深げになる。しかし暫くすると鳶色の頭を俯かせてしまった。
「……できぬ……」
「…なにゆえ」
「薩摩は封建の厳シ藩じゃ。俺のような郷士に、そげん力はなか」
「…力は生まれながらに付随するものではない。手に入れるものだ」
「!」
「お前は、出来る。俺には分かる」
そこまで言うと、正助の体からそれまでとは異なる気が発せられた。
単なる希望ではない。子供から出るはずのない酷く冴えた、そう、まるで月影のような光芒。
ほら、照っているではないか。お前は既に。
…必ずなれるよ。
俺が小さく呟くと、ごくりと喉を鳴らして、正助が言ってきた。
「お前……何者だ…」
響いたのは、創世の為だけに命を与えられた者特有の、冷酷な声。こうして俺の素性すら見抜いているのがその証拠である。
――――そう、それでいい。
「清水寺成就院第二十四世住職」
「え…?」
「我が名は月照。いずれお前が照らす者」
「…っ!」
「月に焦がれてここまで来た。…早う男になれ」
俺には決して為し得ない、世を照らすほどの、漢(おとこ)に。
月と日は、相対(あいたい)するものにて互いの軌道を駆け巡る。
それは永劫向かい合い、重ねも離れも致さない。
ひとつが欠ければ他方も散りて、世界のあしたも消え失せるべし。
